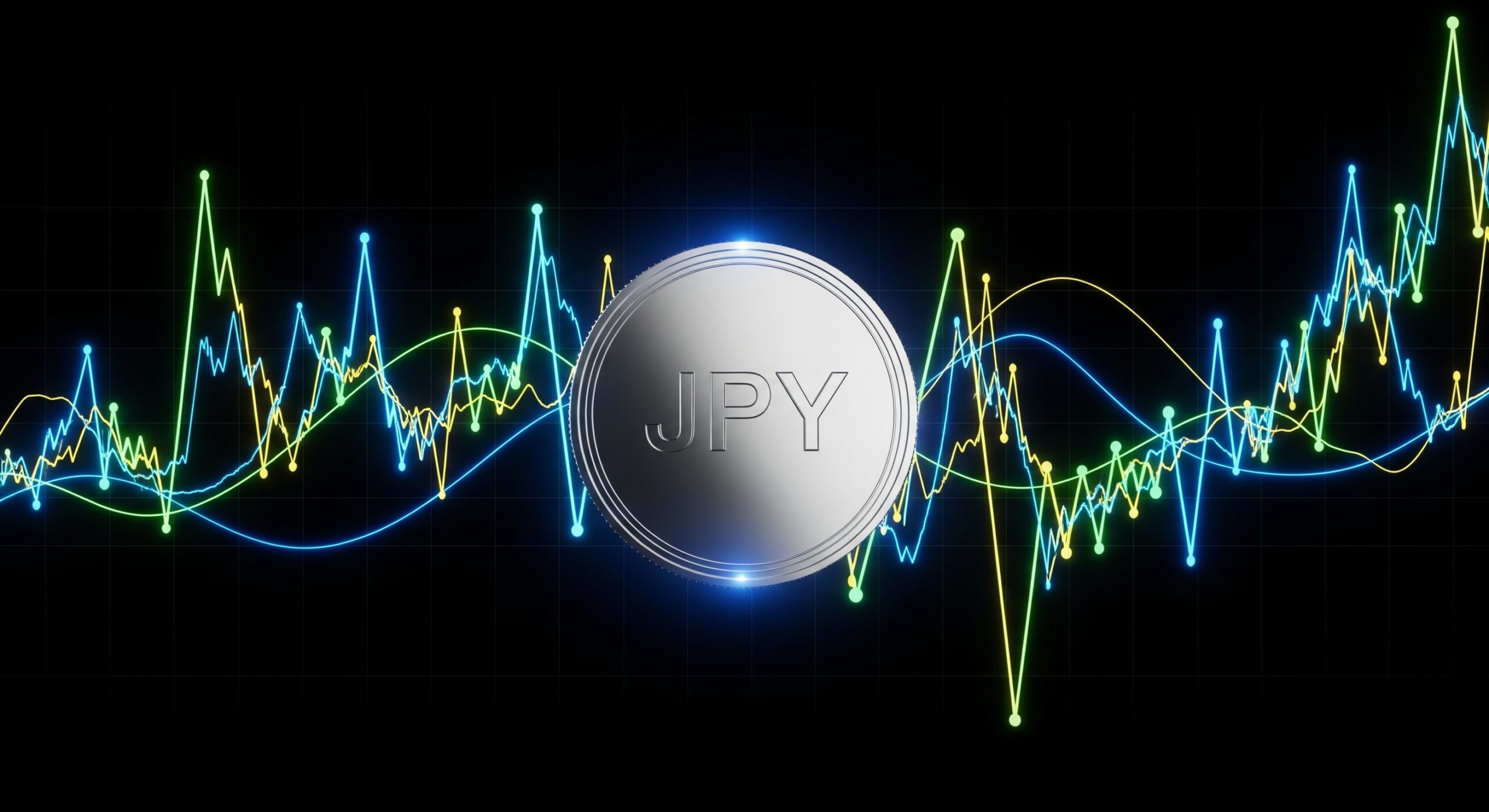SNSで「日本円ステーブルコインJPYCさん、ついに暴落」という投稿が拡散しました。しかし、価格が1円から乖離した事実はあるものの、これを「暴落」や「デペッグ」と表現するのは、当該資産の法的な性質を根本的に誤解しており、「ミスリード」と判定します。現在取引されている「JPYC Prepaid」は、現金との交換が法律で原則禁止されている「前払式支払手段」であり、二次市場での価格変動は、その法的制約から生じる自然な結果です。
検証対象
2025年8月頃、X(旧Twitter)などのSNSで「【悲報】日本円ステーブルコインJPYCさん、ついに暴落」という投稿が拡散。価格が1円を割り込んでいるとされる市場データと共に、JPYCの信頼性や安定性に疑問を呈する声が上がりました。これに対し、「それはプリペイド式の旧バージョンであり、規制下のステーブルコインではない」「金融庁に認可されたステーブルコインはまだ発行されていない」といった反論も多く見られました。
結論:ミスリード
「JPYCの暴落」という主張は、資産の法的分類を無視した、誤解を招く表現です。一方で、ユーザーからの反論は、概ね正確な事実を指摘しています。
- 「JPYC暴落」という主張について → ミスリード
現在流通する「JPYC Prepaid」は、現金償還が保証された真のステーブルコインではありません。法的に「前払式支払手段」に分類され、発行者による現金での払戻しが原則禁止されています。そのため、二次市場での価格が需給によって1円から乖離することは、ペッグの失敗(暴落)ではなく、法的制約による自然な価格変動です。 - 反論1「これはステーブルコインではなくプリペイド式」について → 概ね正確
指摘の通り、取引されているトークンは規制下のステーブルコインではなく、プリペイド型の「前払式支払手段」です。 - 反論2「金融庁認可のステーブルコインはまだ発行されていない」について → 正確
JPYC株式会社は、2025年8月18日に規制下のステーブルコイン発行の前提となる「資金移動業者」の登録を完了しましたが、2025年8月24日時点で、新しい法律に準拠したステーブルコインはまだ市場に発行されていません。
検証の詳細
1. 「暴落」の真相:市場価格の変動と「デペッグ」の決定的違い
市場データを見ると、「JPYC Prepaid」の価格が1円から乖離して取引されていることは事実です。しかし、これを一般的なステーブルコインの「デペッグ(暴落)」と同一視することはできません。
USDCのような真のステーブルコインは、発行者が常に1トークン=1ドルでの現金償還を保証しています。市場価格が0.99ドルになれば、裁定取引者が安く買って1ドルで償還することで利益を上げ、価格は1ドルに引き戻されます。この償還メカニズムこそが、価格を安定させる錨(いかり)です。
しかし、「JPYC Prepaid」にはこのメカニズムが存在しません。なぜなら、次に説明する法的な理由により、発行者であるJPYC株式会社が1トークンを1円で現金に払い戻すことが原則として法律で禁止されているからです。そのため、その価値はDEX(分散型取引所)などの二次市場における需要と供給のみで決まり、価格が変動するのは当然の帰結なのです。観測された価格変動は、技術的欠陥や信用の失墜ではなく、資産設計に内在する法的制約が市場で顕在化したものです。
2. JPYCの2つの顔:旧「前払式支払手段」と新「電子決済手段」
この問題を理解する鍵は、JPYCが準拠する法律が二種類あることを知ることにあります。
① JPYC Prepaid(現在流通しているトークン)
これは、資金決済法における「前払式支払手段」という枠組みに基づいています。これはSuicaや楽天Edyのような電子マネー、あるいは商品券と同じ分類です。この法律の最大の特徴は、無許可の預金や送金を防ぐため、原則として発行者による現金での払戻しを禁止している点です。JPYCが2021年にサービスを開始した際、日本にはステーブルコインの法律がなかったため、この既存の枠組みを利用して市場に参入しました。価格が変動するのは、この「払戻し禁止」ルールに起因します。
② 規制下のJPYC(将来発行される新トークン)
2023年6月に施行された改正資金決済法により、日本で初めてステーブルコインは「電子決済手段」として法的に定義されました。これを発行できるのは、銀行、信託会社、そして国に登録された「資金移動業者」のみです。この新しい枠組みでは、発行者は常に利用者からの請求に応じて1トークン=1円での償還(払戻し)が義務付けられます。JPYC株式会社は、この新しいステーブルコインを発行するため、2025年8月18日に関東財務局から第二種資金移動業者としての登録(関東財務局長 第00099号)を完了しました。これにより、同社は将来、完全に1円にペッグされた、真のステーブルコインを発行する資格を得たことになります。
3. 混乱の原因:JPYCのバージョンと名称の変遷
ユーザーが混乱する一因に、JPYCの複雑な製品履歴があります。初期のV1トークンからV2へのアップグレード、そして2024年11月には、将来の新しいステーブルコインと区別するために、既存のV2トークンを「JPYC Prepaid」へと正式に改名しました。さらに、この移行に伴い、2025年6月1日には「JPYC Prepaid」の新規発行を停止しています。
一般ユーザーから見れば、「JPYC」という名前から円との1:1の交換を期待しますが、その裏側にある「前払式支払手段」という法的制約や、複数のバージョン履歴は分かりにくいものです。この「期待」と「法的現実」のギャップが、今回の「暴落」騒動の直接的な原因と言えます。
| 特徴 | JPYC Prepaid(既存の旧トークン) | 規制下JPYC(将来発行される新トークン) |
|---|---|---|
| 法的分類 | 前払式支払手段 | 電子決済手段 |
| 準拠法 | 資金決済法(改正前) | 改正資金決済法(2023年施行) |
| 発行者ステータス | 前払式支払手段発行者 | 登録済み資金移動業者 |
| 日本円への償還 | 原則として法律で禁止 | 法律で1:1の償還が保証 |
| 価格安定性 | 二次市場の需給変動に依存 | 保証された償還により円と1:1でペッグ |
| 現状 | 発行済み、DEXで取引、新規発行は停止 | 未発行(2025年8月時点) |
判定に至った理由
以上の検証から、「JPYCが暴落した」という主張は、資産の法的性質を考慮しない、誤解を招く表現であると結論付けます。現在流通している「JPYC Prepaid」は、法的に現金償還が原則禁止された「前払式支払手段」であり、その価格が二次市場で変動することは仕組み上の必然です。これを、償還メカニズムが破綻した時に使われる「暴落」や「デペッグ」という言葉で評価するのは不正確です。
FACTCHECK Scienceのコメント
JPYCを巡る一連の出来事は、日本におけるステーブルコインの黎明期を象徴しています。既存の法律を工夫して利用した「前払式支払手段」の時代が終わりを告げ、専用に設計された「電子決済手段」という新しい時代の幕開けが近いことを示しています。JPYC株式会社が資金移動業者として登録を完了したことは、日本のWeb3エコシステムにとって極めて重要な一歩であり、将来的には法的に安定したデジタル円が、企業間決済やDeFi(分散型金融)など、様々な分野で活用される可能性を秘めています。この事例から得られる教訓は、いかなるデジタル資産においても、その名称やマーケティングだけでなく、その価値と挙動を決定づける根底の法的・規制的枠組みを理解することの重要性です。